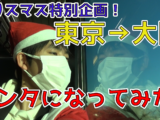私とドジョウ
私は、日本産淡水魚が好きであり、とりわけ、ドジョウの仲間は大変好きである。ドジョウという魚は、だれもが一度は耳にしたことがある日本で最も有名な魚の一つであると思う。
先日、ネットサーフィンをしていると、戦前から戦後にかけて「ドジョウ列車」なるものが走っていることを知った。その列車の正体とは、一体何か?とドジョウの食文化について執筆していきたいと思う。
ドジョウとは?
ドジョウとは、コイ目ドジョウ科に属し、東アジア各地に分布する魚である(中島ら,2017)。池沼や水路、水田、河川中・下流域に生息し、皮膚呼吸や腸呼吸と呼ばれる特殊な呼吸方法によって、低酸素下でも生息することが可能である(中島ら,2017)。

ドジョウ列車についての記録
インターネットでドジョウ列車について調べると、以下のような記述がみられた
①新潟県亀田町,見附市周辺で年間200トンを超えるドジョウ生産があり、土用の丑の日ごろに東京方面に「ドジョウ列車」が運転された。(新潟県HP https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/97500.pdf)
②青森県津軽地方では、戦後に五能線沿線(五所川原駅)から多くの「ドジョウ列車」が運転された。(http://www.mutusinpou.co.jp/%E3%81%BE%E3%81%A1%E3%83%8D%E3%82%BF%E6%95%A3%E6%AD%A9%EF%BC%81%E9%99%B8%E5%A5%A5%E6%96%B0%E5%A0%B1%EF%BC%88%E7%B6%9A%E3%80%85%EF%BC%89/2014/11/33839.html)
③新潟県亀田郷では、戦時中ドジョウ列車を仕立てられた(http://www.kamedagou.jp/koho/100/dojyou.html)
④新潟県では、専用のドジョウ列車が多く仕立てられ、東京市場に送り込まれた(https://www.jstage.jst.go.jp/article/nogeikagaku1924/53/1/53_1_N1/_pdf)(日本農芸化学会誌1973年53巻1号)
と主に、青森県津軽地方と新潟県亀田町・見附市から大消費地東京にドジョウ列車が出ていたことがよくわかる。
特に新潟県亀田町付近は、亀田郷と呼ばれた田園地帯であった。また、「芦沼」や「地図にない湖」とも呼ばれた。そのような沼のような環境は、人が稲作をするのには大変厳しい環境だが、ドジョウが生息するには適した環境であり、年間200t以上とることも納得できる。
なぜドジョウなのか?
今はほとんど食べられていないドジョウがなぜ「ドジョウ列車」が仕立てられるようになったのか?その原因は、大きく分けて3つあると考える。
①運搬しやすい魚であるから
ドジョウは、先述の通り、低酸素下への耐性が非常にあること知られている。さらに、水がなくなっても、湿った土があれば、ドジョウは土の中に潜って、越冬することもできる魚離れした魚なのである。
今でこそ、クール便や冷蔵車が存在するが、戦前から戦後にかけては冷房がついた列車はなく、劣悪な環境で大都市まで運ばざるを得なかった時代があった。そのときに、どんな環境にも耐える強かな魚「ドジョウ」は重宝されたのであろうと考えられる。
(参考として、1964年10月の時刻表によると、新潟から上野(信越・上越・高崎線経由)が、普通列車で10時間程度・特急列車「とき」で5時間程度かかった。)
②栄養価が高い魚であるから
「ドジョウ1匹 ウナギ1匹」という言葉があるように、ドジョウ1匹の栄養価はウナギ1匹に劣らないと表す言葉だ。ドジョウとウナギの大きさは、大きく違うがそれでも負けず劣らずなのである。

ご覧の通り、カルシウムや亜鉛など多く含まれている。また、カロリーや脂質はウナギより低く、ヘルシーな食材である。また、コラーゲンも多く含まれている。ドジョウは、栄養面からみても、大変有用な魚なのといえる。
③市場価値が高い魚であるから
1976年のドジョウ1kgの東京卸売市場の金額は、単月当たりの平均金額は、1000円~2000円を示しており、日によっては3000円から4000円と高値で取引されるようになった。(https://www.jstage.jst.go.jp/article/nogeikagaku1924/53/1/53_1_N1/_pdf)(日本農芸化学会誌1973年53巻1号)
このように、高値で取引されることも多く、農家の副業としてドジョウとりがメジャーになったと考えられる。
ドジョウの食文化とは?
ドジョウの食文化は、各地に存在する。特に、ドジョウの大消費地であった東京では、柳川鍋やかば焼きにして食材にされていたようである。

ドジョウ列車はなぜなくなったのか?
ドジョウ列車がなくなった原因として、ドジョウの個体数の減少や、輸送形態の多様化、国産ドジョウの衰退があげられる。現在、ドジョウは、多くが外国産のものを使用している。
ドジョウを後世につなぐために
現在、ドジョウは、環境省より「準絶滅危惧」に指定されている。原因としては、ドジョウの仲間であるが、外来種である「カラドジョウ」との競合や、生息環境である水田や水路、湿地などの減少があげられる(https://www.nikkei.com/article/DGXMZO30847660T20C18A5000000/)。私たちとってなじみ深いドジョウが準絶滅危惧に指定されたことは、各種メディアで多く取り上げられた。さらに、ドジョウはドジョウであっても、由来が中国大陸であるドジョウが増加している。大阪府で発見されるドジョウのほとんどは、この中国大陸由来のドジョウがほとんどを占めていることが分かった(松井・中島.2020)。
ドジョウのみならず、私たちのなじみ深いミナミメダカは、ニホンウナギは、に指定されている。私たちにとってなじみ深い魚が、(場合によっては)将来居なくなるかもしれないのである。
これらの状況を踏まえ、ドジョウを守るために、私たちができることは以下の3点である(中島.2017)
・放流をしない
・野生採集個体の売買をしない
・生息地の情報をむやみに公開しない
ことである。
おわりに
今回の記事は、ドジョウが好きな鉄オタが書いたもので、話の流れがスマートではないと思う。しかし、多くの人に、ドジョウ列車やドジョウについて知ってもらえばうれしいこと限りない。